皆さんはこれから、マスコミとは異なる業種・職種の転職先で、新たなキャリアを築いていきます。これまでに培った取材力や文章執筆力などのポータブルスキルは生かせるでしょうが、一方で新たなスキルも身に付けていかなければなりません。ただ私が新聞記者から転職した当時と比べて、最近は生成AIの発展とともに、ホワイトカラーの仕事がどんどん減っていくことが指摘されています。これから活躍していくために、どのような姿勢でスキル形成に努めるべきなのでしょうか?
新たなスキル形成の課題と向き合うために

私の個人的な経験に基づく転職指南という趣旨から、本サイトでは事業会社の広報職への転職を推奨していますが、皆さんはそれぞれの考えのもとで転職先を選定していると思いますので、ここでは個別具体的なスキルについては言及しません。
ただ広報に限らず、昨今はAIの急速な発展に合わせてホワイトカラー不要論が叫ばれたりしていますし、ジョブ型雇用が注目される中で「より専門性の高いスキルを築くべき」との意見もよく目にします(ちなみに私はこの記事で触れたように、ジョブ型雇用は日本には定着しないとの見方です)。
私が新聞記者から広報に転職した当時と比べても、社会を取り巻く環境が大きく変わってきているのは事実で、今回はこのような中、一般論として転職後にどのような姿勢でキャリアを築いていくべきなのかを考えてみたいと思います。
幸か不幸か私は現在、プロフィールに記載の売上高1兆円以上の企業で管理職を務めていますので、転職当時の経験というより、皆さんを受け入れる立場の視点で考察します。
ホワイトカラーの未来とAIの台頭
さてAIの登場でホワイトカラーの仕事がなくなるのかというと、私の(無責任な)予想では、かなりの業務が置き換えられるのではないかと見ています。
置き換え可能な業務のリストは様々な機関が発表しているのでそちらに譲るとして、例えば私の抱える具体的な業務として、あるプロジェクトを遂行する際に必要なタスクリストやスケジュール感、体制図などの素案は、それこそあっという間にAIが提案してくれます。
よくAIに対する批判としてクオリティがまだまだ低いということが挙げられたりしますが、あくまでたたき台を提案してもらっていると思えば、細かい部分は自分で修正していけばよいわけです。
また大変残酷な話ですが、あえて不都合なことから目をそらさずに申し上げますと、大半の部下に依頼するよりもクオリティは高く、納期は厳守(というか即時提出)であり、はっきり言ってほとんどの人間とは勝負になりません。
不正確な回答をすることは事実ですが、それはAIへの期待が高すぎるということでもありますし、あと数年もしないうちにまたクオリティは上がるでしょう。
日本企業、特に大企業は高齢化が著しく、保守的で新しいテクノロジーへのアレルギーもあるので、浸透にはしばらく時間がかかるかもしれませんが、きっとPCやインターネット、メールやチャットのように、仕事のツールとしてAIを活用していくことになるのは間違いありません。
ではヒトはどこで勝負すればよいのでしょうか?
AIと人間、どこで勝負するか
あくまで現段階ではと注釈付きになりますが、先述したようにAIはまだまだ不正確な回答を出してきます。
しかし、しかしなのです。何度でも言いますが、大半のヒトはAIに及ばない成果物しか出せず、納期に遅れることもしばしばで、おまけに言い訳までしたりするのです(そうです、私みたいにです!)。
そのうえ文句も多く、人間関係で揉めたり信じられないほどサボろうとしたりと、とにかく労務管理が大変です。
私が負担しているわけではないので構わないのですが、これで年収ウン万円ももらっているのかと考えると、経営者は本当にやり切れないと思います。
で、私がAIが本当に優れていると感じるのは性能が高いことではなく、この管理に手間がまったくかからないという点なのです(経営的な視点で言えば、コストも人件費よりはるかに安いですよね)。
罰ゲームと言われていることから分かるとおり、管理職として部下を取りまとめるのは結構大変です。(自分も含めて)ヒトは嘘をつくし、ごまかすし、不満は多いし、直接的な人件費以外にも、動いてもらうためには心労を含めてコストがかかります。
「それ私の仕事なんですか~?」と口をとがらせる部下を説得して、方向性と期限を示し、仕事をお願いしたにも関わらず、締め切りには遅れるわ、方向性とずれた成果物が上がってくるわ、それを指摘すると「指示があいまいなんです」とこれまた口をとがらせるわで、だったらAIをフル活用して自分で軽く手直しした方がコストも時間もかからないよね、というのが現段階でのAIとヒトに対する評価となります。
だから「どこでAIと勝負するか」という命題に対する残酷な回答は、①まだ不完全なAIに劣らない成果物をつくる、②管理の手間がかからない人材になる、の2点に集約されるのではないでしょうか。
そしてさらに残酷なことに、①は早晩AIの性能の向上により達成が難しくなり、せめて②だけでもやらなくては、という未来が近くやってくる気がしています。
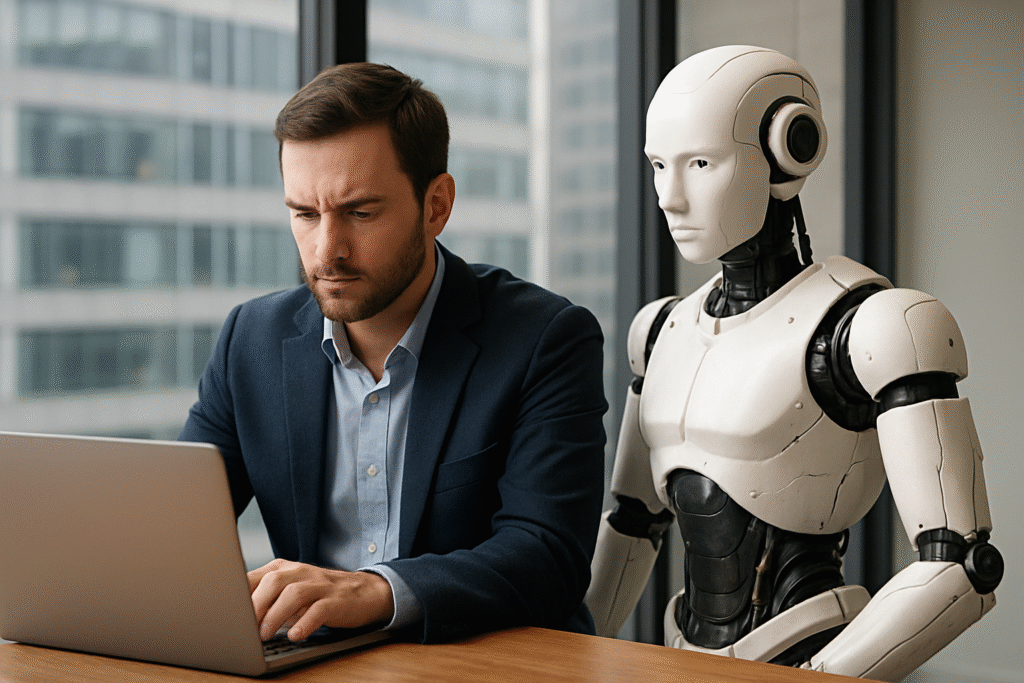
人格こそがAI時代の最大の武器
なんだか私情が入ってくどくなってしまいましたが、つまりスキル形成はAI導入の遅い日本企業ではまだまだ大切なものの、それは近い将来、陳腐化する恐れがありますので、スキルとともにいわゆる人格を磨いていくことが大切だと主張したいのです。
急に飛躍して、また自己啓発系の洗脳っぽくなってしまって自分でも嫌なのですが、いわゆる問題社員とまではいかなくとも、扱いづらい社員の居場所は今後どんどん少なくなっていくと予想します(解雇規制の厳しい日本では、どこかの目立たない部署に押し込まれるのでしょう)。
能力でAIに勝てないにも関わらず、管理の手間ばかりかかるヒトとは、誰も一緒に働きたくありません。
私は前々から言っているように「能力よりも人格」が大切という考え方で、それはヒトが仕事の主体だったころから変わらないと思っています。
しかし大人数のヒトを活用するしか仕事のレバレッジが効かなかったころは、扱いづらいヒトも必要経費として織り込まざるを得なかったことでしょう。
しかしAI時代の到来でそのような必要はなくなりました。能力があろうとなかろうと、そこではどのみちAIには勝てないので、一緒に働きたいと思える人格こそが大切になるのです。
簡単に言えば、仕事できる風な頭でっかちになるのではなく、またマスコミ的な一匹狼を気取るのでもなく、親しみやすい常識人たれということです。
AI時代の仕事の構造と戦略的キャリア形成
そもそも論として、スキルや能力というものは「人に使われる」上で必要になるものです。
世間ではスキル向上だのリスキリングだの騒がしいですが、ある程度キャリアを重ねたら、自分ではなくそうしたスキルの高いヒトを活用して、より大きな仕事に取り組むことをおススメします。
なお現段階では、いわゆる現場仕事はなくならないと思います。
これらの仕事をする方々はエッセンシャルワーカーとも呼ばれ、その役割は尊いものですが、ものすごく単純化して見れば、AI時代の仕事の流れの中では以下のように位置づけられるでしょう。
上流には気の合う仲間同士で大きな仕事の企画をするヒトがいて、中流にはその企画を受けて詳細な業務設計を行うAIがいる。ただしAIは肉体を持っていないので、AIのつくった指示のもと現場仕事をヒトが実行するというふうに。
これがユートピアなのかディストピアなのかは分かりませんし、上記は私の単なる予測なので外れる可能性は大いにあります。
ただ大企業の管理職としてこう思うことは事実であり、異業種・異職種への転職を果たした皆さんには、やみくもにスキル獲得競争に身を投じるのではなく、戦略的にキャリアを築いていってほしいと願っています。
AIが代替する中流の大部分をこれまでホワイトカラーが担っていたことは事実なのですから。





コメント